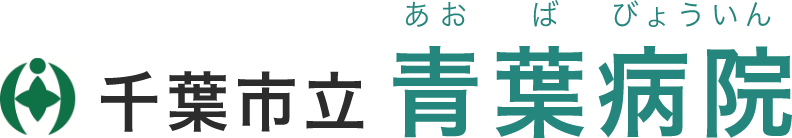リハビリテーション科

リハビリテーション科ではけがや病気、障害などによって低下した身体機能や生活能力、コミュニケーションの障害等に対して、失われた機能の回復を促すとともに残存能力を最大限に引き出すための治療を行い、患者さんが家庭復帰や社会復帰ができるよう支援をする診療科です。
当診療科で行う治療手段には理学療法、作業療法、言語聴覚療法があります。患者さんの状態にあわせてこれらの治療法を組み合わせて効果的に実施します。
特色・治療方針
千葉市立青葉病院リハビリテーション科では、患者さん一人一人に寄り添い、最適なリハビリテーションを提供することを大切にしています。
・リハビリ専門医が常駐する病院
当院のリハビリテーション科には日本リハビリテーション医学会の認定するリハビリテーション科専門医が常駐しており、医学的管理の下で効果的なリハビリを提供します。
・急性期から生活期まで切れ目のないリハビリ
当院では、急性期の早期リハビリテーションを重視し、入院直後から積極的にリハビリを開始し、機能回復と早期退院をサポートします。地域の医療機関や施設と連携し、退院後も安心してリハビリを継続できる体制を整えます。

・多職種連携による包括的なケア
医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・栄養士・医療ソーシャルワーカー等がチームで支えるリハビリを行っています。カンファレンスを通じて情報共有を徹底し、患者さんにとって最適なリハビリ計画を立案します。

・患者さんの「できる」を増やすリハビリ
画一的なプログラムではなく、その人に合ったリハビリを提供し、可能性を広げるサポートをします。また、患者さんが自らの回復に積極的に取り組める環境づくりを目指します。
リハビリテーションの目的
1.機能回復:失われた身体機能(運動、呼吸、循環、言語等)をできる限り回復させる
2.能力向上:回復が難しい場合でも残された機能を最大限に活用する
3.生活の質(QOL)の向上:日常生活や社会参加ができるよう支援する
4.再発、悪化の予防:健康維持や再発防止のためのトレーニング、生活指導を行う
疾患別リハビリテーション施設基準
- 運動器リハビリテーション(Ⅰ)
- 脳血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)
- 呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)
- 心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)
- 廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ)
- がん患者リハビリテーション
主なリハビリの種類
理学療法
主に起きる、座る、歩くなどの基本動作にアプローチし、離床を促したり、運動能力の回復や維持、自立した移動・日常生活動作の回復を目指します。200平米以上のゆったりとした屋内訓練室に加え、全周100mの屋外歩行練習場もあります。

作業療法
生活能力の向上を目指して、各種作業を行いながら上肢機能、心身の回復や日常生活動作、応用動作にアプローチします。
また、児童精神科にも1名配属されており、集団療法などを行っています。

言語聴覚療法
主に口腔機能、嚥下機能、言語機能にアプローチし、患者さんの「食べる」「話す」を中心にサポートしています。

対応疾患
当科で取り扱う各種疾患のリハビリテーション
1.運動器リハビリテーション
主に整形外科からの依頼で、入院・外来の骨関節疾患の患者さんに対して手術前後(周術期)のリハビリを行っています。
- 運動器疾患とは骨、関節、筋肉が壊れたり変形したりして生じる病気の事です。特に当院では人工股関節置換術、人工膝関節置換術、人工骨頭置換術、観血的整復固定術、脊椎固定術、椎弓切除術、下肢切断等の術前後のリハビリテーションを実施しています。
また、上肢機能のリハビリテーションも取り扱っており、人工肩関節置換術、腱損傷、上肢全般の骨折などの手外科に対する作業療法、装具療法にも対応しています。

2.脳血管疾患リハビリテーション
脳・脊髄及び末梢神経などの病変によって運動に障害をきたす疾患のリハビリテーションを行っています。
代表的な疾患としてパーキンソン病、ギランバレー症候群、脳炎、脳梗塞等があげられます。症状、障害に応じたリハビリテーションが必要であり、運動機能だけでなく、高次脳機能障害に対してもアプローチしています。
患者さんの残存機能を最大限に活用し、日常生活能力の向上に努めます。必要に応じて福祉用具の選定、家屋環境調査を実施し安心して自宅復帰ができるよう支援しています。

3.呼吸器リハビリテーション
呼吸器疾患を持つ患者さんが、より快適な日常生活を送れるようにするための包括的なプログラムを提供し、息苦しさ(呼吸困難)の軽減や運動能力の向上、生活の質(QOL)の改善を目指します。
代表的な疾患として慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺気腫、間質性肺炎、誤嚥性肺炎等があげられます。
また、感染症病棟を完備しており、COVID-19、結核等の患者さんにも適切な感染対策を実施の上、対応しています。
4.心大血管疾患リハビリテーション
心臓リハビリテーションとは運動療法を中心とした生活習慣改善のための総合的なプログラムです。代表的な疾患として心筋梗塞、心不全があげられます。
心臓病を患ったことの不利益を少なくし、突然死や心臓病の再発リスク、症状を軽減し、動脈硬化の進行を防ぎ、患者さんの社会的地位を高めることを目的としています。当院でもリハビリテーションの内容は運動療法による身体機能や運動耐容能の改善のみならず、冠動脈危険因子の改善に必要な栄養指導や禁煙指導、服薬指導、家族に対する指導など多職種がかかわり、多くの内容を含んだ包括的な内容となっています。
また、心筋梗塞後のリハビリテーションでは、急性期である入院中、運動負荷による合併症(不整脈の出現や心機能の低下など)が起こるかどうかを評価しながら、医師、コメディカルによる個別的な運動療法を実施します。段階的に運動強度や活動量を増やし、決められたプログラムに沿って進めていきます。退院後は3か月頃まで、集団での外来心臓リハビリテーションを実施し、社会復帰するまでの準備期間として徐々に身体活動の範囲を広げ、生活習慣是正のための教育、食事指導、職場復帰のためのカウンセリング等、退院後のフォローアップをしています。

5.廃用症候群リハビリテーション
長期の入院や安静が続くと、筋力や体力が急速に低下し、日常生活に必要な動作が難しくなることがあります。これを「廃用症候群」と呼びます。筋力低下だけでなく、関節のこわばり、呼吸機能の低下、起立性低血圧、さらには認知機能の低下など、心身に様々な影響を及ぼします。
例えば、ベッド上での安静が1日続くだけで、筋力は2~3%低下し、1週間で約10%、1か月後には約50%も低下すると言われています。特に高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、影響が出やすく、元の生活に戻るまでに長い時間がかかります。
当院では、こうした廃用症候群を予防・回復するために、できる限り早期からのリハビリテーションを行っています。ご本人の体調や状態をみながら、無理のない範囲で離床(ベッドから起きること)を促し、筋力や呼吸機能の維持・改善を図ります。
リハビリの内容は、座る・立つ・歩くといった基本的な動作訓練から、日常生活に必要な動作の練習まで多岐にわたります。また、ご家族へのアドバイスや退院後の生活に向けた支援も行っています。「寝たきりにさせない・戻さない」事を目標に、私達はチームでサポートしています。
6.がん患者リハビリテーション
がんの進行や治療によって受けた身体的なダメージに対してリハビリを行うことで日常生活の向上や仕事復帰を目指します。がんやその治療によって身体的問題が生じると生活や仕事が困難となり、生活の質(QOL)は低下してしまいます。リハビリを行うことで回復力を高め、日常生活動作(ADL)やQOLを向上させることが期待できます。当院入院中はがんに対する治療とリハビリが並行して行われます。がん自体による局所・全身の影響・治療の副作用・安静にしている期間や悪液質(がんの進行による全身の衰弱した状態)に伴う身体状態に大きく左右されます。病状の変化に則してがん治療のいずれの段階においてもリハビリテーションは大きな役割を担っています。
特に外科術前(消化器外科等)の呼吸筋トレーニング、術後の早期離床、早期ADL訓練を実施したり、白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの造血器のがんに対する造血幹細胞移植前後では化学療法や全身放射線照射に伴う副作用や合併症によりベッド上安静となる事が多く、廃用症候群に陥りやすくなります。できるだけ早い段階で予防的に介入し、治療中も体調に合わせて有酸素運動を取り入れたり、筋力訓練を実施していきます。
また、緩和医療が主体の時期には患者様の要望を尊重しながら、身体的、精神的、社会的にもQOLの高い生活が送れるように援助していきます。
7.摂食嚥下のリハビリテーション
「食べる」という行為は脳の指令で食べ物を認識し、口やのどを動かして水分や食物を口に取り込み、胃へ送り込むことです。この一連の運動を摂食嚥下機能と言います。この運動に支障をきたし、食物を飲み込もうとすると気管へ入ってむせてしまう、食道へ入っていかずのどに残ってしまう、という症状が特徴的に見られます。
摂食嚥下障害で生じる問題は肺炎・窒息・低栄養・脱水などの生命の危険に直結する深刻なものばかりです。また、食べる楽しみを失うというQOLの観点からも重要な問題になります。当院ではリハビリテーション科医師・耳鼻咽喉科医師・神経内科医師・歯科医師・言語聴覚士・作業療法士・看護師・栄養士・薬剤師が摂食嚥下機能サポートチーム(SST)をつくり、患者さんが安全かつ楽しく生活できるよう、食事や栄養摂取の方法を確立することを目指しています。
8.児童精神科作業療法
当院には全国でも少ない児童精神科専用病棟があります。児童精神科病棟では、子供たちの心の健康を支え、社会的・情緒的・身体的な発達を促進するためのリハビリテーションの一環として、多職種と連携し、プログラムを行っています。
遊びや創作活動、体を使う活動などをその時に参加する子供たちに合わせて実施しています。また、日々の病棟生活などで身体的な不器用さや学習の困難さ等が見られた場合は、主治医の指示で個別のプログラムを行うこともあります。
対応できない疾患について
当院リハビリ科の役割として、入院患者の急性期のリハビリを重点的に対応させていただいております(外来は退院後のフォローのみ対応しております)。
回復期・維持期の入院リハビリや外来リハビリは、回復期病院、介護保険、外来クリニックなどでのリハビリをご利用いただきますよう、お願いいたします。
診療体制
診療体制・スタッフ
リハビリテーション科医師 2名
横にスクロールしてください。
| 氏名 | 資格 | 専門分野 |
|---|---|---|
| リハビリテー ション科部長 輪湖 靖 |
日本整形外科学会専門医 人工関節学会認定医 日本整形外科学会リウマチ認定医 |
リハビリ テーション ・整形外科 |
| 主任医長 青墳 佑弥 |
日本リハビリテーション医学会専門医・指導医 日本内科学会総合内科専門医 日本神経学会専門医・指導医 日本臨床神経生理学会専門医 |
リハビリ テーション ・神経内科 |
横にスクロールしてください。
理学療法士(PT) 11名
作業療法士(OT) 8名(児童精神科配属1名)
言語聴覚士(ST) 2名
取得資格
横にスクロールしてください。
| 取得資格名 | 人数 (名) |
|---|---|
| 日本理学療法士協会登録理学療法士 | 6 |
| 日本作業療法士協会認定作業療法士 | 1 |
| 日本理学療法士協会認定理学療法士(代謝) | 1 |
| 日本糖尿病療養指導士 | 1 |
| 認定臨床教育者(認定CE) | 1 |
| 日本心臓リハビリテーション学会心臓リハビリテーション指導士 | 1 |
| 一般社団法人日本循環器学会心不全療養指導士 | 5 |
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 7 |
| がんのリハビリテーション研修会修了者 | 21 |
| 千葉県地域災害派遣医療チーム(CLDMAT) | 2 |
| 臨床実習指導者講習会修了者 | 16 |
| ICLSプロバイダーコース受講修了者 | 5 |
| 医療クオリティーマネージャー | 1 |
横にスクロールしてください。
診療実績
横にスクロールしてください。
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入院内訳 | 脳卒中その他脳疾患・脳外傷 | 92名 | 109名 | 129名 |
| 脊髄損傷その他脊髄疾患 | 26名 | 37名 | 56名 | |
| リウマチを含む骨関節疾患 | 660名 | 448名 | 669名 | |
| 脳性麻痺を含む小児疾患 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 神経・筋疾患 | 36名 | 50名 | 32名 | |
| 切断 | 3名 | 6名 | 4名 | |
| 呼吸・循環器疾患 | 798名 | 990名 | 1,136名 | |
| その他 | 817名 | 878名 | 981名 | |
| 延べ患者数 | 32,381名 | 32,809名 | 41,917名 | |
横にスクロールしてください。
横にスクロールしてください。
| 疾患別リハビリテーション延べ件数 | 入院(件) | 外来(件) |
|---|---|---|
| 脳血管疾患リハビリテーション(Ⅰ) | 4,958 | 52 |
| 運動器リハビリテーション(Ⅰ) | 7,899 | 3,247 |
| 呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) | 10,509 | 1 |
| 心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ) | 3,588 | 329 |
| 廃用症候群リハビリテーション(Ⅰ) | 6,662 | 0 |
| がん患者リハビリテーション(Ⅰ) | 4,407 | 0 |
横にスクロールしてください。